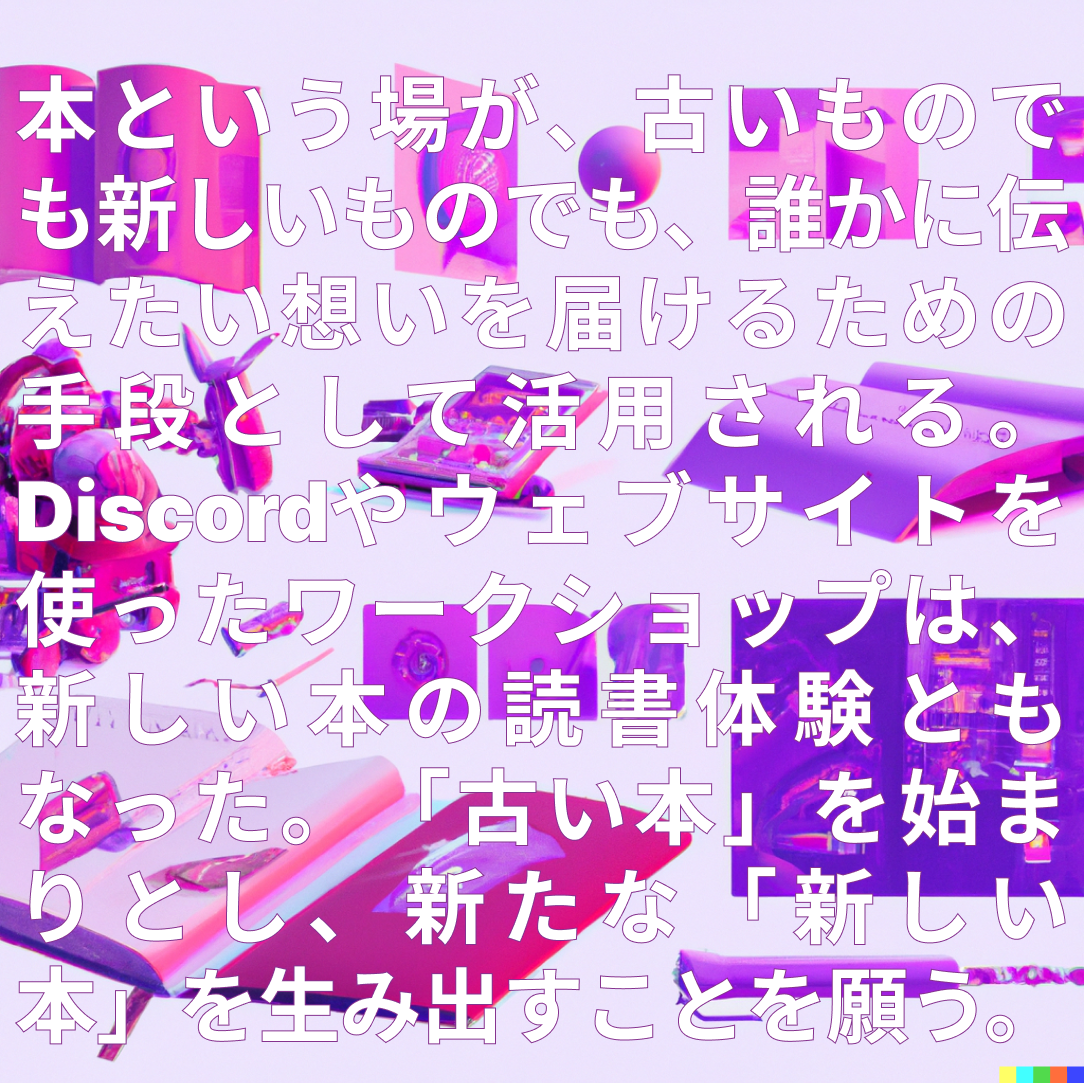2023年3月3日に、昨年10月より6ヶ月に渡り開催していましたSFプロトタイピングWSの最終発表会を行ないました。
ワークショップの概要はこちらになります。
発表会当日は、各チームの講師4名大澤博隆さん・宮本道人さん・長谷川愛さん・樋口恭介さんとチームメンバー、本寄付講座の講談社とメディアドゥの方もご参加いただきました。
発表会はzoomで行ない、トークのみならず、チャット欄も大変賑わった時間になりました。
以下、各チームの成果物についてレポートします。
本を食べることが日常的になるのかも?(Aチーム)
講師: 大澤博隆先生
構成員:○平澤彰悟(渡邉研)、hao cao(渡邉研)、Shuto Takashita(東京大学制作展)、柳与志夫(寄付講座教授)
・成果物の紹介
モデリングしたのか!
合成音声すごいですね
デザインが可愛いけど不思議な毒感もありますね
食べないと生活に害が出るというところが面白いです
暗記パンみたいなものですかね?
質問: 技術的に近い研究とかあるのでしょうか?アイデアのヒントになったものなどもあれば教えていただきたいです
暗記パン、憧れた記憶があります!
情報における三大栄養素みたいな概念が生まれるかもですね!
本の情報が食材になるのは面白いので、その食材から料理にどうなるか、もう一工夫あると面白そうです
本の在り方だけでなく、メンタルヘルスや苦境に立たされている編集者という職業の在り方など、現代におけるそのほかの課題についても言及されていて、その点で非常に広がりのある発表だったと感じました!
コンピュータを介してデータを入力して、植物が育つという観点が面白いです。
料理には、食材だけでなくスパイスも不可欠であり、調味料次第でより美味しさや素材の良さが引き出せることもあるかと思います。「食べる本」の調理工程において、そのような、”スパイス”の役割を担う要素は、一体何になるのかな、とワクワクしました!
SFプロトタイピングを通して紡ぎ出された「新しい本」をめぐるSF小説・SF論文集(Bチーム)
講師:樋口恭介先生
構成員:○大井将生(渡邉研)、中村健太郎(渡邉研)、周寧(渡邉研)、原田真喜子(渡邉研)、中橋さん(東京大学制作展)、冨倉由樹央(講談社)
・手法
・SFプロタイピングの手法を用いて三度のmeetingディスカッション
・Discordを用いて議論の拡散・雑談
・SF作家である樋口恭介先生の助言のもと、メンバー各自が「新しい本」をめぐるSF小説や異常論文を執筆
・HPを作成し、制作したSF小説・論文を電子書籍(epub)・PDFでリリース
・成果物の紹介
(成果物のSF小説・論文を電子書籍でご覧いただけます)
・作品タイトル・著者紹介(実在しないAIメンバー含む)
“夢の本、本の夢/樋口恭介 | ウォルポニストの彼女/中村健太郎 | あなたにおすすめの本は/冨倉由樹央 | 町にひらかれる立ち読み本/中橋侑里 | 殖える本/菊池洋子 | 墓前本/原田真喜子 | 実験教育都市・図書街におけるキュレーション学習/大井 将生 et al.”
・感想
本という場が古いものでも新しいものでも、誰かに伝えたい想いを届けるための手段として活用される。ZoomやDiscord、Webサイトを用いたチームBのSFプロトタイピングWSは、新しい本の読書体験ともなり、そこには確かにセレンディピティが存在した。
おお,もう観られるのか
無駄にかっこいいぞ
販売しなくていいいんですか>樋口先生
後で読みたいです!
大丈夫です!
イラストも素敵です
セレンディピティの基盤として、オープンの思想を取り戻すというのも一つのコンセプトです
Team-Bです。よろしくお願いいたします。以下に成果発表に関する情報を貼らせていただきます。【Team-B成果物=SF小説オムニバス作品Webページ】https://kokima.sakura.ne.jp/team_B/上記ページ内から電子書籍(epub)、PDFでダウンロード、閲覧可能です。(大井論文形式のみ原文フォーマットが異なりますのでよろしければ以下よりご笑覧ください。)https://researchmap.jp/m-oi/published_papers/41567037/attachment_file.pdfWS各回のレポート詳細は下記講座HPよりご覧ください。第1回WSレポートhttps://www.new-book-project.jp/2022/10/sfws.html第2回WSレポートhttps://www.new-book-project.jp/2022/11/sfws.html第3回WSレポートhttps://www.new-book-project.jp/2022/12/sfws.html*なお、本日このあと18:30より、Team-Bの講師も務めていただきましたSF作家の樋口京介先生をお招きして、東大のB’AIというプロジェクトのイベントで「SFプロトタイピングの話かそうではない話」というテーマでご講演いただきます。申込不要ですので是非お気軽にご参加ください☆Zoomリンクも以下ページ内にございます。https://baiforum.jp/events/en039/
あらゆること・・・!
ざっと読んでみてますが,どの作品も面白いですね。
異常論文もあるし
😆
AIが文章を書くというのは、もはや確実な未来ですよね。
大人気作家が実はAIだったなんてこともありそうですね
すごいですね!これによってsf世界の本の地図も作れるかんじですね。
“新しい本の設計、及び小説の大まかな設定や新しい本の特徴を説明するようなシーンの設計は、予め筆者が行なった。小説生成〈AIのべりすと〉を利用しながら、全体の構成や展開の大きい部分から、背景描写や人物の行動など細かい部分までを、詰めていった。AIが提示した展開をそのまま採用することはなく、適当にフィードバックくれる友人や先生という認識であり、参考にしつつも自身で記述していった感じである。例えば、この言葉遣いは後で参考になりそうなど、特に小説を書いたことのない筆者にとって、AIが提案する言葉遣いは非常に参考になった。画像は、画像生成AI〈midjourney〉で生成。新しい本の設計と小説を書き終えた後、想像通りの情景を生成させるのは困難であった。小説を書きながら画像を生成すれば、画像からインスピレーションを受けて、文章をつくることもできるだろう。” 中橋さん解題より
絵に関しては、僕が差し込んだものに関しては、小説をchatgptに読ませて、dalle二に指示するpromptを突くてもらって書きました。一個あたり10分かからなかった感じです
AIを使って文章や短い小説などを書くことで、自分の知らない自分の考えを知るということがどんどん普通になっていくのかなと感じました。
*dalle2です
ブラウザを複数立ち上げて、AIを大量に稼働させて、そこから人間が選定する発想はなかった!!
自分も活用したのはdalle2デス。楽で楽しかったです
でも一枚あたり30案くらいは出しました。捨て案がすごい出たので、精度を上げる部分は僕が細かく編集したりもしてます
この作品自体が“SFチック”で、メタっぽい雰囲気があって素敵です
Dalle2が作った捨て案はこんなかんじです https://www.dropbox.com/sh/sbdhng2zq3pk37i/AAAwrbb1nNxwb36NbYnz27PXa?dl=0
読むところの補助もAIがしてくれる、という感じにはなりそうですね。要約技術のように
一部ですが。この五倍くらいあります。AIの生成は、メタメッセージがうまく揃わない感じはあって、コツがいるなあって気はしてます
Bチームのみなさまお疲れ様でした~ ありがとうございました!
動画生成AIが普及したら、小説がすぐに映画になるかもしれませんね
どのチームも面白いですね。WSやってよかった
未来の1日をロールプレイすることで生み出された未来の街歩きのための雑誌構想「月間 東京人」(Cチーム)
雑誌かっこいい・・・!
生産過多で消費が追いつかねえみたいなのは、AIが消費=金を払うようになると解決すると思ってます。
現実的な具体論で言うと、データのアクセス制御とAPIの有料化ってことになるんやろなあ、と思います。
なるほど。「読む」のに金を払う,という意味では同じですよね。本を買うのと。
本の経済=APIエコノミーになる。
ドアに嫌われると家にはいれないのいいすね
「読む」の意味は広くなりました!
60年皇居のドアだったドアに小説書いて欲しいっす
爆撃されているウクライナの土地に私小説書いてほしい
話それますが、建築の研究者だった人間としては、メンテナンスやリペアの自動化には興味あります
他方でメンテナンスやリペアが自動化されると、必要が蒸発して発明がなくなりそうやなとも思います。AI派人g年の最終発明ってきはします。タイポしました。大規模言語モデル=意識みたいなものの発明は、人類の最終発明って気がします。
意識みたいなものというか、意識と区別できないものですね
それてる状態で勝手にしゃべっちゃいますが、兵器も意志や感情を持ったらおもしろい。「俺の素材はウクライナで生まれたから、ウクライナは攻撃しない」とか言って、爆発を拒否する爆弾とか出てくる。
実際AIの人権の話はすぐ出てくると思うし、それはおそらくアメリカが黒人や女性に段階的に参政権を与えてきた歴史にある程度そうものになる気がします。
海の物語、読みてえ
モノの意識に介入できたら、道に迷った時に道自体に聞くといったことができそうですね。道が書いた街のガイドマップとか面白そう!
全部ソラリス化する
GPT-4はソラリスと区別できなそうですよね、、
奥さんの首の後ろの縫い目が…
他方でmatrixのアーキテクトみたいな役割を担わされるAIも出てきそうす。
「本の体験」が普通になってからの未来、私たちの価値観はどう変わっていくのか? - 意外と簡単に突き抜けることのできない想像の限界に挑戦してみた(Dチーム)
構成員:○ヤン ケビン(渡邉研)、金甫榮(渡邉研)、柴田さん(東京大学制作展)、山口温大(渡邉研)、藤井喜久(講談社)
・手法
・成果物の紹介
・感想
最初のアイデアからガジェットの実装に向かって議論していくと、どうしても段々現実または我々の知見に寄り添っていくような傾向がある。そうするとなかなか飛躍的なSFにならないことを途中で気づかされる。LARPデザインを実施したり、最初のゴールよりさらにその先を目指してみたり、様々な試みを行なった。あとはAIとの本気の恋愛とかもわりとすぐそこってきがします
人以外を創作のサイクルに入れることで、市場というかマーケットが広がるのはいいなあ、と感じます
セカイカメラって昔ありましたが、あれの拡張版と考えると実現可能な気がしてきました
理屈上は人間の頭数*生涯賃金にマーケットサイズが制約されるはずで、やはり樋口先生のAIが金を払うっていうアイデアはかなり熱いですね
古着屋のそばでその年代のファッション歴史が読めればいいですね
実際、AIに娯楽を提供するのが人類の役割とかになりそう
A班の媒体がどう変化するか、B班の誰が書くのか、というテーマと対比して、“誰が読むのか”という発想がすごく新鮮で楽しかったです!
AIが金使えるようになると(国の考える、経済としての)少子化問題も一発解決です
この発表を聞いて、中沢新一のアースダイバーを思い出しました。
アースダイバーを、語られてきた側から語るっていうコンセプトですよね。
人工物がある種のセンサーであるっていう見方はすでにあって、それが現実化するのはおもしろいですね
街が自分について書き始めるとき、街には自分がどういう街になりたいという意思を持つんですかね? 街が、居住者や来訪者を選ぶようになったり、税金的なものを徴収するようになったり。そしたら、街(=AI)が自分のために金を払うということもありそう。
眼鏡をかけた後以前の世界の様子が見えるですね、イラストかっこいいです
法廷では「証拠品に語らせる」わけですが、そのコストがめちゃ下がるわけなんで、街が意思をもつのもぜんぜんありそうです
個人的に好きな話なんですが、古代ローマでは「モノ」を被告人にした裁判というのがあって、例えば教会の金に百年の島流しの刑がくだる、みたいなことがあったらしいです
というかAIが意識を持つなら、AIトロッコ問題も解決しますね。普通にAIに罰を与えれば言い訳なので
いや前段としてAIに職業選択の自由を認めないとだめだ。むずかしいすね
そうですね。ヒトが介在しなくても,モノや空間どうしが会話していても,ぜんぜん自然。
「読む」という本と人間のインタラクッション方式も場所によって変えるが面白いです!
紙媒体のファッション・美容雑誌の発行が打ち切りになるといった、雑誌購読の文化がだんだん薄れているというニュースを以前目にしました。一方で、『地球の歩き方』もcovidで売り上げが落ちた中、国内・地域に絞った特集を組んで、売り上げを回復させた、というニュースも聴きました。このプロジェクトは、雑誌購読の機会が停滞している現代にて、「人」以外も相互にmainに取り込んでおり、雑誌読者のターゲット層を拡大すると感じました。
その場合、言語自体は必要ですか?
物語を生成するコストがゼロに近づくなら、物語を本の形で保存しなくてもよさそうですがね。口伝による伝承の時代に一気に戻りそうです
とにかくChatGPTがスゴすぎて、えらいことになったなっていうふうに思ってます。安全保障とか位置から組み直しだし、ワンチャン世界大戦ですよね〜
言語の話ですが、僕は音楽に近づきそうと思ってます。
人間が世界を解釈するために最適なシンボル化をしたものが言語なので、人間以外の場合は必ずしも同じ言語にはならないだろう、とは感じます。言語創発の観点では
これとかみてると特に思います。メジャーコードでポジティブになる、マイナーコードでネガティブになる、その組み合わせを設計して、最後に最初のコードに戻してハーモニーをつくる、みたいな技術が音楽だそうなので、だとすれば音楽で文字が読めなくとも任意の心理状態を再現性を持って作り出す、みたいなことは可能そうです。
ワーグナーはナチスのための音楽を作ってたわけで、まあそのようなテクノロジーの使い方もありえますね
chatGPTとstabledifusionのアルゴリズムの違いで、Diffusion Modelで言語学習ができない点おもいだしました。https://sander.ai/2023/01/09/diffusion-language.html
そろそろお酒を回したい感じになってきましたね
どのチームもやるなあ…笑
Diffusion model初耳です。attentionを使ったtransformerとはまた別なんですかね
すご
すごいす
すご
面白いわ
迫力がハンパない
ストーリーの飛び方がおもしろすぎですね
やっぱり物語の設計論みたいなものがAI使う上で有用になりそうっていう気がしました。ハリウッドが得意そうなやつ。
どのチームもすごすぎて、廃業しようかな?って気持ちになってきました
陰謀論に嵌める技術とか今の段階でもふつうにつくれそうですよね〜
どこの発表もあたらしくて,揺さぶられますね。ふだんの大学の作品制作課題とは根っこから違う
AIと小説を書く方法の本書けばめちゃくちゃ売れそうです
それだ
一攫千金を狙いましょう
ツルハシを売るタイミングに立ち会えるとは思ってませんでした
ゴールドラッシュや。。
令和のリーバイスをつくりましょう
最近、chat GPTって検索すると、アフィブログがめちゃヒットして本物にたどりつけない感じになっててウケてます
相対的にwikipediaの価値が爆上がりしているっていうツイート見て首がもげました、今朝
あと、今はKDPで画像生成AIによって作成されたエロ本がクッソ増えてて、チャリンチャリンビジネスが始まってます。
AI生成エロ本を見て「AIと人間の尊厳をかけた戦いや」って葛藤している人のツイート見てわろいました。おととい
「負けました」ってツイートしてました(失礼しました)
五感を使ってみる。めちゃくちゃヒントもらっちゃってます。ありがとうございます。
俺も自分の小説音読しながら書くか…
>Diffusion model初耳です。attentionを使ったtransformerとはまた別なんですかね
俺も自分の小説音読しながら書くか…
>Diffusion model初耳です。attentionを使ったtransformerとはまた別なんですかね
別の技術パラダイムですね。stablediffusionのやつです
ノイズつけてもどす学習させるものですね
若者に大人気の無料自撮りアプリ「SNOW」が、480円有料で「aiアバター」機能を追加したのですが、それがSNSでかなりバズっていて、私も頻繁にその投稿を見かけます(自分の顔の原型を残しつつ、AIがより完璧な姿にしてくれるのです)冒頭の動画は、現代のこの流行が更に進化して、実際に我々の身体に落とし込まれた場合、あり得る未来なのかもと想像しておりました。
ノイズつけてもどす学習させるものですね
chatGPT(transfomerもこれ)は次元(ニューロン)増やして行列化して、例えばMountainとかは正確に1文字ずつ行列化してでしか認識できないんですが、difusionモデルはノイズつけて戻す学習で絵をかけるようになったので、ノイズつけてもどすものであれば音楽やらできるらしいんですよね。多分口頭での会話は学習できるっぽいですが、テキストができないという。つまり僕らの話している言葉は適当という意味なのかなと。
あそれおもしろいですね。
Mountain=山って1ピクセル違っても山と認識できるけど
Chatgptは行列化0,1にしているので、この1ピクセルの精度をもとめないといけないんですよね
なるほど。ちょっとその辺また伺いたいです〜(質的データ分析の自動化に興味あっていま)
Attentionモデルはそうですよね、入力をベクトルにしなきゃいけないらしいので、、
(attentionモデルという言葉はおそらくないです)
その問題で先程のattentionモデルは限界がくるって知り合いのGoogleのAI研究者が言ってました、ので今回のワーク通して人間ベースや記号ベースでないAIの学習方法はわりと重要なのかとおもいました。
コスパよい学習
dalle2はtransformerベースって見たんですよね。その辺も興味あります
新しい技術・状況に対する出版社の方の粘り強さ、特に電子化や国際化も手掛ける講談社さんの活動は大変楽しみにしています(これは作家クラブ側としてもそう感じます)。
A班とD班にコメントしてなかったので、コメントを。A班:食べる本、場所のデザインまで考えるともっと面白そうですね。フレンチとか和食とかどんなレストランがあるのかとか。D班:僕、電車の中で本を読んで、よく笑ったり泣いてて、変な人と思われてるだろうなといつも思ってます(笑) 本と、人に見られる表情、面白いテーマだと思います。